2025.05.06
島民インタビュー
島に暮らして10年。迷いながらも自分なりの幸せを見つけ、歩み続ける。
今回は、横浜から下甑島の手打地区へ移住してこられた松田さんにお話を伺いました。
松田さんが手打に来られたのは今から10年前の29歳の時でした。手打にあったおじい様の家の維持管理が大変だからもう解体しようという話が出たタイミングで、「もったいないから、俺行くわ!」と移住を決心。
「いろいろと道に迷っていた私は、これは行くしかない気がしたんです」と振り返ります。
当時、横浜で経営していた飲食店をスタッフに任せて島への移住を決めた松田さん。20歳で会社を起こし、自営でいろいろやってきたので、島でもきっと何かしらできるだろうと思っていました。
ちょうどその頃に、下甑島での地域おこし協力隊の募集を見かけ、応募。地域おこし協力隊員として、廃港になった旧手打港の待合所を再利用したレストラン「てうちん浜や」をオープンすること、また、島の特産品を使った商品開発のミッションを遂行することとなりました。


任期中には、島の特産品を使った様々な商品を開発しました。写真は、こしきのかおり・オーガニックエッセンシャルオイル。ほかにも、キビナゴのアンチョビ、きびなごを塩漬けした時の塩をキビナゴ塩として販売したり、フレグランスエッセンシャルオイル精油、精油とこしきの塩と混ぜたバスソルト、こしきハニーのハチミツの初期パッケージのデザイン、イベントのポスター制作などなど多数の商品開発プロジェクトに関わりました。
様々な想いの狭間で生きる
地域おこし協力隊の任期終了後も、「てうちん浜や」の運営を任され、順調に進んでいくかと思われていました。しかし、新型コロナの流行により営業が難しくなってしまいました。アルバイトの雇用も厳しい状況が続き、ひとりで店を切り盛りするようになって少し経った頃に、GO TOトラベルが始まりました。
それまでの静けさが嘘のように、毎日50~60人が来店する日々が1ヵ月続きました。ときどき手伝いに来てくれる方もいたものの、松田さんは休む間もなく働くことになりました。その結果、体調を崩し倒れてしまい、ドクターヘリで本土の病院に搬送され、入院することに。
そんな中でも島に残してきた仕事の事が気掛かりだった松田さん。「自分がやらないといけない、仕事しなきゃ、島に戻らないと」と治療を途中でやめて、島に帰ってきました。
その後も必死で働きます。そして、無理がたったてしまい、仕事が出来ないほど寝込むことが増え、遂には店を閉店。そして、島を離れることになりました。
「真面目すぎたんです…もうあんなに頑張らない。もう頑張るのはやめようって思いました」と当時を振り返ります。
「地元に帰るでもなく、生活の為とりあえず働くだけなら鹿児島でもいいか。ゆかりもない鹿児島にいるんだったら別に横浜でも…」と思いながらも、「まだちょっと島に未練とかあるからここにいるんだろうな…」という想いで、鹿児島市内で暮らしていました。
鹿児島市内での生活も1年が過ぎようとしていた頃、下甑島・手打にあるビジネスホテルベイ(宿泊施設)の管理の話があり、再び下甑島に戻ります。
これまでを振り返り「なんかね、もう人がいる場所って縁ですよね」と松田さんは言います。


島に帰ってきて、ビジネスホテルベイの運営をしながら、何か新しいことをしたいと思っていたそうで、その少し前からブロックチェーンやNFTの勉強を始めていた松田さんはいろんなプロジェクトにも参加していました。
ブロックチェーン:分散型のデータベースで情報を暗号化し安全に保管する技術
NFT:デジタル版の『所有権の証明書』
支援者と共に挑む島のクラフトビール事業
また、所属しているカバードピープル(くだらないことにこそ価値があるをモットーとして、独特の世界観とアートを武器にインターネットを中心に活動しているクリエイティブコミュニティ)のNFTプロジェクトのひとつを自分の仕事と繋げられないかなと模索していました。
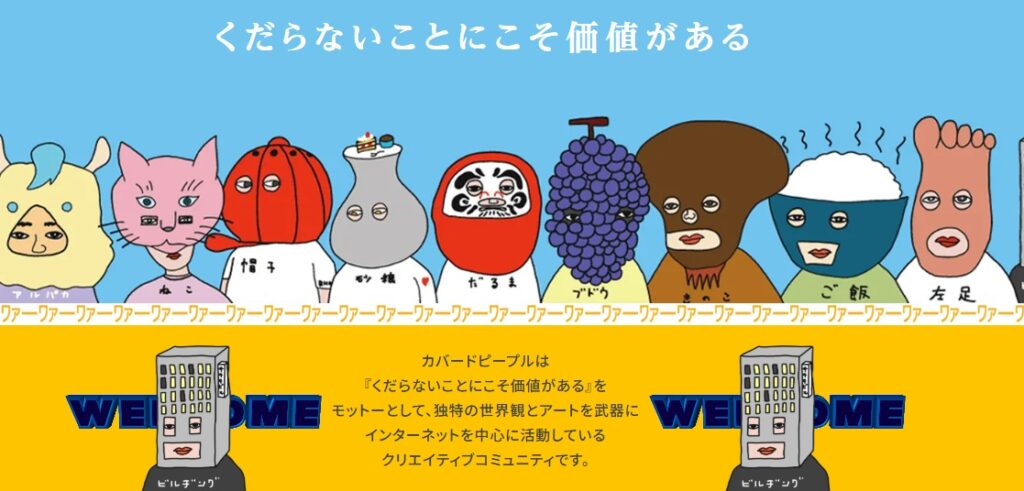
そんな時、横浜時代の友人から「美味しいから飲んでみろよ!」と送られてきたクラフトビール。とても美味しかったことを友人に伝えると、友達は冗談半分で「じゃあ、松田、お前もビール作れよ!」と言い出し、笑いながらもその言葉がきっかけに、じゃあ、作ってみようか!と突如、甑島にビール工房を作ることになります。


思いがけず始まったクラフトビール工房の建設は、カバードピープルとクラフトビール作りを融合させた新しい事業へと発展。NFTを通じて、建物の所有権を持つオーナーを募集した結果、300名を超える支援者が集まりました。
市からの補助も決定し、工事も進行し順調に進んでいるかのように見えましたが、松田さんに再び試練が訪れます…補助金の決定が突然取り消される事態に直面。「、、、終わった。」と一瞬は絶望の淵に立たされましたが、すぐに気持ちを切り替え、諦めることなく、再度補助金の申請や銀行、公庫への融資交渉を重ね、何とか再始動を果たしました。
「ビールが今ここに無いのに応援してくれる人がいるのって凄いことなんです」
「後戻り出来ない状況ではありましたが、諦めずに続ける事が出来たのは300名を超える支援者の方がいたからです。やる!って始めたのは自分だけどもう自分一人のプロジェクトではなくなっていて、良い負担がかかり続けているんです。やるしかない!」
真面目で、一生懸命でついつい頑張りすぎてしまう松田さんには応援し、支えてくれる支援者、コミュニティの仲間たちがいます。共にプロジェクトを楽しみながら進められることは、何よりも心強いことでしょう。応援する周りの存在が、松田さんの挑戦をより一層輝かせているように感じます。



ビール工房について熱く語る様子を再現してくださっている松田さん!
プロジェクトをきっかけに、島への縁を紡いでいく
コミュニティの方の中には、このプロジェクトをきっかけに島を訪れるうちに、「やっぱり甑島いいなぁ」と感じ、移住を決断した方も。ビール工房での働き手を求めていたタイミングでもあり、松田さんから紡がれた島との縁がつながりました。
「今は甑島に移住してください、と直接勧める時代ではなく、別の方法があるのだろうなと感じてきました」と松田さん。「支援者の方々、約300名の方が、縁もゆかりもなかったこの甑島に謎の縁を感じて、まるで聖地のように思っている。実際に昨年も30名ほどの支援者が島を訪れて、工房の現場を見て『わぁー!』と感動して帰っていくんです。こうした交流を続けていけば、人生のどこかのタイミングで甑島で暮らすことになったり、必ずしも常に島にいる必要はないけれど、関係人口としてつながり続けることができると思うんです。」

興味関心を持った約300名のうち、昨年、実際に島に訪れた方が約30名(約10%)だそうです。これは、色々なところが発信してる観光情報に何万人アクセスして数十名程が来るという時代に、10%の訪問者が実現しているという点で、非常に高い割合だと感じられます。
「この打率を維持できれば、観光で島に訪れる人が増えるだけでも島内でお金は動くじゃないですか。そういうのが伸びていくといいなと思うんですよね」と松田さん。
「自分がやったことの結果が地域の活性に繋がっていればいいな。だからってしようと思ってするものではなく、自分たちが楽しいなと思えることをやれたらいいと思っています。島でもここを起点に何かできたらいいなって考えてます。」
そんな松田さんのビール工房作りの事を知った地域の方からも「協力したい」との声を頂くようになったそうです。島内外のたくさんの人が『KOSHIKI BREWERY(こしきブリュワリー)』のオープンを心待ちにしています。


趣味のように仕事を楽しむ
宿泊業、革製品の製造販売、お土産等の企画開発、ビール工房と様々な事業を展開する松田さんは自分の仕事に関して「全部副業だし、全部が趣味って言いたい」と話します。
「無責任さであるとかプライドがないとかそういうことではなく、全部副業って言えるくらいがちょうどいいんです」
好きな仕事だからこそ、できるだけ楽しく続けたい。真面目に仕事をしていればしているほど、精神的に疲れる事が多くなるからこそ、あまり自分を追い込まず、自然体で楽しむ趣味と言えるくらいの気持ちでやれるといいのかもしれません。
自分がいる場所で出来る事をやるだけ。声がかかれば、そこに行きそこで出来る何かをするだけ。
「だからなんかね、ある意味、気持ちが自由になるんですよ。今このデジタルコミュニティに同じような概念を持って集まっている人たちがたまたま周りにいてくれるからなんかとりあえず老後も寂しくないかもしれないと思うんです。」
松田さんは、デジタルコミュニティの良さについて、「少し疲れている時や気分が乗らない時には、自分からネットにアクセスしなければ離れられるところが良い点」と話します。
また、その環境と同じように、自分のペースで気軽に距離を取れる余白のある島の暮らしの良さを話してくださいました。
「ただ空を眺めている時間がとても贅沢。家の前でぼーっとしてることもよくあるんです。空は青いなーって。雲はなんで白いんだろう。俺って満たされてるー。こんなボロい家だけど屋根あるしな、ありがたいなみたいな。ほんとにありがたいなーって、感謝できるんです。島に来てただ空が青いなって感じて、帰っていくだけでもいいんじゃないかって思います。」
心のゆとりを持ちながら暮らせている心地よさが伝わってきます。



「幸せの濃度が濃くなる」心の豊かさと人生観
「都会にも田舎にもそれぞれの良さがあり、全部同じ物差しで図ろうとしがちですが自分が育ってきたところの尺度で見ると、劣ってたりとか悪いとことかなんか色々あるけどどこも変わらないと思うんです。便利だったり不便なのはあるけど、別にもう、電気が通ってて水道があって。インターネットが来てればどこも同じ。ただamazonがなかったら島暮らしは出来ていないね」と笑う松田さん。
また、「島にいると、平和そのものだなと感じて色々な事に鈍感になっていく」と話す松田さんは、定期的に昔からの趣味であるナイトハイク(夜登山)で、恐怖を”摂取”しにいっているそうです。かつて、精神的に追い詰められた時には、恐怖を感じなくなった経験も話してくれました。真っ暗な夜の海を見て「怖いな~」って思った瞬間、精神状態が正常に戻ったことを実感したそうです。
「恐怖を味わうことで、あぁ、生きてるな~って、自分は生きたいんだな~、生きることに執着してるな~って感じて、生きたいと思えてることを再確認しています。」
「美味しいものを食べた時とかに、あぁ~幸せって思うのとかも濃度が濃くなるんです。それで、太陽が暖かいなぁ~ってだけでもすごく幸せに感じらるようになった。これからも凄くデジタルなことをしながら、とても人間にフォーカスして生きていけたらいいなぁと思ってます。」
試練と決断の連続の中で立ち止まりながらも、自分なりの幸せを見つけ歩み続ける松田さん。

最後に移住を考えている方へメッセージをいただきました。
「移住みたいなものってすごい神聖化されてる気がします。島でこれをやってやろう!って感じで来るよりも、なんとなく来てもいいと思います!」
「都会的な概念であるとか、社会実装されてるわりと当たり前とされてることの尺度ではない視点で島を見てみると、良き島ライフが送れるんじゃないかなって思いますね!」
島との縁を紡ぎ、繋げていく松田さんの人生と島の暮らし。迷いながらも、一歩踏み出してみると、その一歩が、自分なりの幸せを見つけるきっかけになるかもしれませんね。
